結論
リーダーシップが伺える戦略。安定した資金繰り、業績。良い会社の条件としては揃っているが・・・後は利益分配権を握る人の匙加減次第かな、というところ。
目次
事業概要
まずはULSグループの事業についてです。

ULSグループの事業は顧客企業の競争優位性を支える戦略的IT投資領域におけるコンサルテーション及び受託開発からなるコンサルティング事業です。
特定のパッケージソフトなどを売り込むというより、1社1社のコンサルティングを通じて最適なソフトの導入をサポートする会社ではないかと。
分類するならばコンサルティング会社ですから、基本的に設備投資などは必要なく、資金繰り的には有利なビジネスと言えます。
一方でサービスの質が社員の質にかかってくるため、そう簡単にサービスの量産、複製による規模の拡大はできません。MicrosoftがWindowsを、Appleがi-phoneを売るような、爆発的な急成長は難しいビジネスかと推測します。
セグメントの状況
ULSグループはコンサルティング事業の単一セグメントのため、セグメント別はありません。

主要な顧客が載っているので見てみると、2年連続で前田建設工業とみずほ証券です。この2社の売上を合わせると、売上高の25%を占めています。
一応、どれくらいの頻度で主要な顧客が変わるのかを見てみます。


こうして見ると安定的にみずほ証券が主要な得意先にいて、他の会社はプロジェクト単位、数年単位で入れ替わっているようなイメージなのかな、と。
しかし、最も大きな取引先2社を合わせて売上全体の25%ほどであれば、それほど特定の得意先に偏っているわけではないので、貸倒や業績変動のリスクは比較的少ないと思われます。
業績推移
経常利益率の推移は16.7%⇒18.0%⇒17.5%⇒19.9%⇒20.9%

安定的に成長しており、売上の成長に伴い利益率も向上しています。ずば抜けている、とまではいかないまでも、十分優良な水準ではないかと思います。
経営方針
ULSグループは経常利益を経営指標に置いています。
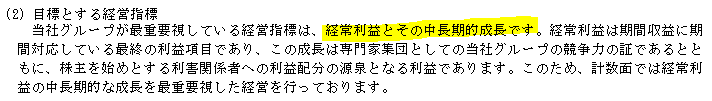
当ブログでは「絶対値指標」と「具体的数値目標の無い指標」に対して否定的です。
絶対値指標を採用すると効率の観点が抜けているため、それだけを求めると、利益率の悪い売上が増えたり、M&Aで規模の拡大を目指したりする事が多く、会社としての質が下がる事が多いためです。
具体的数値目標が無い指標の場合、各担当ごとのKPIに落とし込む事ができませんし、そもそも具体的数値目標が立てられない時点で、「なんとなくそれっぽい指標を言っているだけ」の会社もあるためです。
その基準で考えると、ULSグループの指標は評価が低くなります。
ただ、同社が良いと思うのは経常利益を採用している理由が明確に記述しており、しかも内容が実に的を射ている点です。まさに経常利益とはその企業の競争力の証であり、その中長期的成長はあらゆる企業が目指すべきところです。
(私が業績を見るときに先ず経常利益率を見るのは、その質を見ているためです)
こういった単純ではありながら、的を射た説明ができるのは、経営者が本質を見る事ができる人で、シンプルを貫く勇気が備わっている事の証明ではないかと思われます。
この経営指標の記述からは経営者の質の良さが伺えると思います。
戦略などを読んでみても、まず自社の事業ドメインを明確にできている点も良いです。

また、細かい部分になりますが、言葉の使い方も「採る」「確信する」「行う」「つなげる」と主体的なものが目立ちます。
質の良くない会社は「つもりでいる」「予想される」「考えている」「目指す」といった他人事のような言葉を使う事が多いです。要はあまり結果にコミットする気がなく、逃げ道を残している感が強い。経営者が「何をして、何をしないのか」を明確にできなければ、結局社員も何をしていいのか分からず、成果に繋がるはずがありません。
そうした点からもULSグループの戦略は経営者の意思、考え方がダイレクトに伝わってきて、質が高いものだと思います。
キャッシュフロー

事業内容のところで触れた通り、ULSグループはコンサルビジネスであり、投資は少ないため、フリーキャッシュフローが潤沢です。よほどの事が無い限り資金繰りに困る事はないかと。
ただちょっと5年前の営業キャッシュフローが赤字である点と、4年前の投資キャッシュフローが多いのが目立つので、一応内容を見てみます。

営業キャッシュフローの減は売上債権が増えた事によるもののようです。営業キャッシュフローが売上債権の増によって減る際に考えられる理由は、大別して2つです。
①期ズレ
②売上債権の滞留
①の期ズレならばそれほど心配はいりません。プロジェクト完了時点で売上が確定するビジネスなどの場合、期中のプロジェクト代金が期中に入金されない事があります。その場合、期末時点の売掛金だけが増え、経費だけが出ていくので上記の営業キャッシュフローが減る事があります。これは大口プロジェクトの終わるタイミングに左右されるだけなので本質的問題ではありません。
問題は②の場合です。得意先が実は資金繰りの苦しい会社で、支払ってくれない場合などは、売上債権が前年に対して増える事があります。これが継続すると、会社に売掛金が積み上がり、貸し倒れのリスクも出てきます。
では、この①と②を見極める方法ですが、3つ方法があります。
・経営者のキャッシュフロー分析を見る。
有価証券報告書ではキャッシュフローの分析をしているため、その部分に理由が書いてある事があります。ただ、この時は事業拡大としか書いてません。

確かにこの年、大きく売上が増えています。

ただ、ちょっとこの説明だけでは頼りないです。
キャッシュフローが減った事で懸念されるのは貸倒や不良債権の問題であり、売上が増えたから、というのは表層的な事実に過ぎません。
売掛金が滞留していないかを確認する必要があります。
・売上債権滞留日数を算出する。
債権が滞留していないかを確認する方法は、売掛金/売上×365で、債権が滞留している平均日数を測る事ができます。
問題の平成28年3月の前後の年を含めて3年の滞留日数を見てみます。

上記売上に対して、各年の売掛金残高が1,261,128、1,913,415、1,748,986ですから、それぞれの平均滞留日数は以下になります。
平成27年3月期:107日
平成28年3月期:144日
平成29年3月期:136日
平成28年3月期から悪化しています。
売上が増えているとはいえ、ちょっと怖いです。
ただ、業界によっては支払いが検収後3か月払い~5か月後払いとかは十分あり得るので、製造業(設備投資などで資金繰りが苦しい)をターゲットに含めているULSグループの債権滞留期間としては明らかにおかしいとは言えません。
・前後のキャッシュフローを見てみる。
後は単なる期ズレであれば、当然前後の営業キャッシュフローが大きくなる筈ですから、前後の年を見てみます。

こうして見ると前の年にキャッシュインが偏っているため、平成28年3月期は営業キャッシュフローが赤字になってしまったのかな、と推測できます。
これらを総合して考えてみると単なる期ズレの可能性が高いのではないか、と推測されます。これだけキャッシュフローが凸凹しているのですから、本来なら経営者の分析でもそこに触れて貰いたい気はしますが、どちらかという財務担当の領域なので、同社の財務担当が塩対応なのかな、と。
こうしてみると過去から結構キャッシュフローが凸凹してますから、数年前まで期ズレを起こすような大口プロジェクトが多かったのかな、と思われます。
その点直近の営業キャッシュフローは凸凹が無くなり安定してきています。

これは一部のプロジェクトに依存しないという意味でも良い傾向だと思います。
4年前の投資キャッシュフローが多い点に進みます。

投資有価証券を1.1憶円ほど買ってます。
金額的に結構大きいのでどこかを買収したのかな、と思ったのですが、そういった情報はありませんでした。

ただ、事業上のリスクの所を見ると、多少投資方針について書かれていました。

この事から推測するに、どこかしら有望なIT技術を持つ会社さんに投資したのではないかと。これに関しては良いとも悪いとも言えません。
事業会社が行う投資は私は個人的には否定的です。あまり成功する可能性は高く無い印象ですし、そもそも経営者が隣の芝生の青さに目を奪われて本業がおろそかになるケースが多いからです。
ただ、ULSグループのITコンサルという事業特性上、新たな技術に対してある程度のアプローチが必要なのも事実です。そう考えると、毎年やっているわけでもなく、たまにやる程度であれば質的に問題ないかな、と思います。
キャッシュフローの動きは総じて問題ないかと思います。
B/S(貸借対照表)
資産の確認です。

現金及び預金44.2億円(62.8%)は結構な水準です。流石は設備投資の不要なコンサル業、という所です。
売掛金も16.7億円(23.8%)と多めですが、債権滞留期間を見ると96日ほどです。4・5年前に比べると大分短縮された印象です。これならそれほど心配はいらないかと思います。
投資有価証券は4.4億円(6.3%)もそれなりにあります。

内容は非上場株式が多いようですが、結構アグレッシブな投資方針のようなので、リスクはそれなりに高いと考えた方が良いです。全損しても問題ないくらいのつもりでいた方が良いと思います。
負債、純資産を見てみます。

有利子負債はゼロの無借金経営です。
純資産が56.8億円(80.8%)とかなり手厚いです。そもそもコンサル業はB/Sリスクの少ない業種ではありますが、これだけあれば資産リストの懸念である投資有価証券が全損したとしても十分カバーできます。
従業員の状況、役員報酬
ここに載ってくるのはグループを管理している会社の給与だけではありますが、傘下の会社も同じくらいと推定すると、年齢に対してはちょっと少ない気がします。

コンサルは基本的に人の質がサービスの質に直結するため、報酬は高く設定することが多いです。IT業界は報酬に対してシビアな業界なのでコンサルといえどあまり多くはもらえないにしても、この年齢に対してこの給与は決して高い水準ではないと思います。。
一方で役員の報酬ですが、取締役2名の報酬を合わせて1.5億円が支給されています。

確かに同社の体質はここまで見てきて決して悪くはないですし、戦略などを見ても強いリーダーシップがあるように感じます。経営の質も悪くないと思います。
ただ、同社の社員給与の水準はコンサル業界から見て、そこまで高い印象はありませんし、経常利益率もそれなりに良いとはいえ、ずば抜けているレベルではありません。
そして絶対値という観点からもULSグループは経常利益が13.3億円、包括利益は7.6億円の会社です。
同社の規模でそれだけの報酬を貰うのであれば、サービスの原資である社員の給与水準をもっと引き上げ、利益率も今より向上した上でなければ報酬に見合わない気がします。
どのようにしてこの報酬を決めているか、という部分を見ると。

要は社長であり大株主である漆原氏の独断という事になります。
漆原氏はほとんど過半数に近い株を持つ大株主ですから、問題ある行動をとっても抑止する存在がいません。

そういった方は猶更、自身だけにメリットのある役員報酬は少なく抑えなければ、倫理的に不安です。せめて報酬の決め方を客観的にも分かるような制度化をしなければ、漆原氏がとりたい放題で、投資家は残ったおこぼれを貰うだけ、という構図になりかねないかと。この部分はちょっと投資家心理的に不安です。
まとめ
会社としての方向性の決め方はしっかりしている印象でした。給与水準が低いとも取れるような事も書きましたが、それはあくまでコンサル業というビジネスの性質や平均給与水準と比較した結果であって、一般的な水準から見ればULSグループの給与は決して悪くないのではないかと思います。
ただ、やっぱり役員の受け取っている報酬との格差は結構大きい気がします。特に同社の場合は社長である漆原氏がほぼほぼ株主総会の議決権を持っていますから取締役会も自由にできてしまいます。
やろうと思えば利益が出ようもんなら根こそぎ役員報酬で持って行ってしまう、という事も理屈の上ではできてしまうことになります。
独断専行できてしまう環境だからこそ、その人の報酬に対する感覚が重要になってくるのですが、現在の報酬の設定額や元となる他の条件を鑑みると、少なくとも私の基準ではあまり信用できないかな、と思いました。
本記事は有価証券報告書を元にした筆者の私的見解であり、特定の意思決定を推奨するものではありません。また、内容に対して適切と思われる指摘があれば、迅速に加筆修正致します。
企業分析リンク
www.freelance-no-excelyasan.com